突然、指導者から「片麻痺患者のPT評価を行って」と言われたら?

臨床実習で片麻痺患者を担当したとき、何から評価したらいいのか迷ったことはありませんか?
実は片麻痺患者の評価は、
①歩行観察 → ②検査・測定 → ③統合と解釈
の3ステップに分けて行うと、簡単に整理できます。
本記事では、学生が実習でつまずきやすいポイントを「症例レポートにそのまま活かせる形」で解説します。「痙縮の仕組み」や「歩行チェックの具体例」も整理するので、国家試験対策にも役立ちますよ。
片麻痺評価は難しく感じるかもしれませんが、押さえるべきポイントは限られています。
この記事を読み終えるころには、評価の流れをイメージできるようになるはずです。
片麻痺患者を「評価する前」に押さえておくべきこと

片麻痺患者の評価に入る前に、まず、片麻痺患者の特徴を押さえておきましょう!
中大脳動脈のどこかの血管に血栓が詰まると(脳梗塞)、ほとんどの場合、後遺症が出現します。中大脳動脈は大脳皮質の一次運動野領域に血液を送っているので、当然、その血管の血流が途絶えれば、運動障害が出現します。このように、上位運動ニューロンが障害されると錐体路徴候がみられます。
錐体路徴候は、教科書的には以下の内容が書いてあります。
〜覚えておきたい! 錐体路徴候〜
- 痙縮(痙性麻痺)
- 筋緊張(筋トーヌス)亢進
- 腱反射亢進
- 病的反射出現
- クローヌス出現
これらは、どのようにして起こるのでしょうか?
まず、確認しておきたいことがあります。
別の記事「国家試験の知識を、臨床実習で行う「MMT」や「筋力増強訓練」に活かすには? 錐体路と筋との間で起こっていることをイメージする」で、中枢神経(特に脳)の役割について解説しました。
この時、脳の役割は、下位運動ニューロンに対して「命令と抑制」を行っていることを説明しました。
「命令と抑制」について復習しておきましょう。
〜覚えておきたい! 「脳の役割」〜
- 命令:下位運動ニューロンに対して、筋を収縮しろ!と命令している。
- 抑制:下位運動ニューロンに対して、筋を収縮しすぎず、いい感じで収縮しろ!とブレーキをかけている。いわば、馬のたづなを引いているみたいな感じです。
つまり、「命令と抑制」が破綻した状態が「錐体路徴候」なのです。
具体的にみていきましょう。
まず、脳の「抑制」がきかなくなったらどうなるでしょうか?
先ほどの錐体路徴候を見てみると、
4.病的反射出現
5.クローヌス出現
は、本来、脳の「抑制」がきいている時は出現しません。脳梗塞により、脳の「抑制」がきかなくなったので、出現してしまうのです。
では、
1.痙縮
2.筋緊張亢進
3.腱反射亢進
はどうでしょうか?
これらの異常は同じメカニズムです。
これまた復習ですが、筋は「錘内筋」と「錘外筋」で構成されていることは、先程の関連記事「伸張反射と同時に覚えよう、相反神経支配・Ⅰb抑制・α-γ連関!」の中でも説明しました。つまり、錘外筋はα運動ニューロン、錘内筋はγ運動ニューロンの2本の下位運動ニューロンから興奮を受け取ります。
具体的には、以下の通りです。
〜筋に関わる運動神経の役割〜
- α運動ニューロンが興奮→骨格筋の収縮(骨格筋の短縮)
- γ運動ニューロンが興奮→筋紡錘の収縮(筋紡錘の伸張)
では、脳梗塞になったどうなるのでしょうか?
脳から、「筋を収縮しろ!」との命令がなくなるので、運動麻痺が起こります。そして、「筋を収縮しすぎず、いい感じで収縮しろ!」との抑制もなくなるので、以下のようの反応が起こります。
〜脳梗塞時に起こる運動神経の反応〜
- α運動ニューロンが異常に興奮→骨格筋の過剰収縮(骨格筋の過剰短縮)
- γ運動ニューロンが異常に興奮→筋紡錘の過剰収縮(筋紡錘の過剰伸張)
これが、痙縮という状態です。
つまり、以下のような状態が、脳梗塞の患者で見られる痙性麻痺という状態です。
〜脳梗塞患者に見られる筋の状態〜
「命令」の破綻による運動麻痺 +「抑制」の破綻による痙縮 = 痙性麻痺
この状態では、当然、筋紡錘が過剰伸張しているので腱反射は亢進しますし、骨格筋も過剰収縮しているので筋緊張は亢進します。脳梗塞の後遺症である片麻痺患者の筋は、このような状態になっているのですね。
以上の知識を考えながら、理学療法評価を行う必要があるのです。
片麻痺患者のPT評価の手順

さて、臨床実習で片麻痺患者を担当することになったら、何から評価したら良いでしょうか?
片麻痺患者の身体的特徴は痙性麻痺を呈しているため、動作観察を行うにも、検査・測定を行うにも注意が必要です。理学療法評価の進め方については、別の記事「臨床実習で、ほとんどの学生が理解していない「理学療法評価」とは?」の中で解説しましたが、片麻痺患者の評価も同様の流れで進めていきます。
片麻痺患者の問題点は、大部分が「歩行時の転倒リスク」を考える必要があるため、評価する際は担当する患者の転倒リスクを考えながら進めていく必要があると思います。そのために、まず、片麻痺患者の歩行動作をチェックします。
片麻痺患者の歩行観察はこの2場面に注目!
片麻痺患者は痙性麻痺を呈しているため、特徴的な歩行を確認できると思います。その際、教科書で学んだ正常歩行との逸脱点を歩行観察から確認できるとベストです。
その際、片麻痺患者の歩行はすべてを細かく見ようとすると混乱します。まずは 全体像を確認した上で、「着地の瞬間」と「蹴り出しの瞬間」 の2つだけに絞りましょう。
以下に、私が片麻痺患者を評価する際のチェックポイントを挙げたいと思います。
〜私が歩行観察する際に確認する片麻痺患者の歩行チェックポイント〜
- 全体像を確認
全体を見て、前額面では左右の、矢状面では前後の、動揺性をチェック
その上で、
→頭部、肩甲帯、骨盤の動きを確認
→身体重心がどのように移動しているかを確認
◎以下をチェック!
・背すじは伸びているか?(猫背・後傾していないか)
・頭部の位置は安定しているか?(上下左右の揺れ)
・上肢の振りはあるか?左右差は?
・歩行中に体が左右に大きく揺れていないか?上体のふらつきはあるか?
・左右の歩幅はそろっているか?(リズムの乱れ)
※ポイントは、「森を見て木を見る → 木を見て森を見る」を繰り返すイメージで、全体の歩行リズムと部分の異常を照らし合わせましょう。 - 着地の瞬間(遊脚後期〜立脚初期):全体と局所チェック(体幹、下肢の動き)
→推進力を止めることで、着地足へ床からの力と重心の移動が起こる
→姿勢を崩さないよう、どこかで身体のバランス調整が起こっている
◎以下をチェック!
・足部:かかとから接地できているか?つま先がひっかかっていないか?
足先はどの方向を向いているか?
・膝:過伸展(後方変位)がないか?
・股関節・骨盤:代償的に引き上げていないか?
・体幹:前傾や麻痺側への大きな動揺がないか?
👉 転倒リスクの有無を一番確認できる場面です。 - 蹴り出しの瞬間(立脚後期〜遊脚初期):全体と局所チェック(体幹、下肢の動き)
→推進力を加えることで、蹴り出した足とは反対足へ重心の移動が起こる
→姿勢をまっすぐ保つよう、どこかで身体のバランス調整が起こっている
◎以下をチェック!
・足部:しっかり床を押せているか?
・膝:屈曲が出ているか?
・股関節・骨盤:麻痺側で推進力を生み出せているか?
・体幹:過剰な側屈や回旋がないか?
👉 推進力が得られているかを確認する場面です。
上記のように、歩行の全体像を観察し、各部位を観察することを繰り返します。その際、目視で確認するのは一瞬の場面なので、蹴り出す瞬間(立脚後期から遊脚初期)と着地する瞬間の2つの場面を観察することを意識して下さい。できれば、自分で再現することができれば申し分ないです。目視による歩行観察が難しいのであれば、動画撮影をする必要があるでしょう。いずれにしても、転倒リスクの要因は何かを考えながら歩行動作の観察が必要となります。
2.検査・測定のポイント
次に、歩行観察から確認できた問題点を検証するために、検査・測定をします。歩行動作に見守りや介助しなければいけない要因を、検査・測定により説明できるようにします。臨床実習で学生が行う場合、関節可動域やMMTにより大部分が説明できると思います。
片麻痺患者の場合、その他にブルンストローム・ステージ、筋緊張、周径、バランス、深部感覚のような項目も挙げられますが、結果として乗せておく分には良いと思います。しかし、それら全てを歩行観察の異常を説明するために、統合と解釈で使えるかと言えば難しいと思います。関節可動域やMMTの結果の補足として、ブルンストローム・ステージ、筋緊張、周径、バランスは使えるとは思いますが、まずは、関節可動域やMMTをしっかり検査できるようになってください。
統合と解釈のポイント
最後に、検査・測定で得られた結果(数値)により、歩行観察で確認できた問題点を説明できるようにします。これが、学生が最も悩むところの統合と解釈です。検査・測定で得られた、それぞれの結果を統合し、歩行観察で確認できた問題点を解釈するのです。
「統合と解釈」を行う際、「三角ロジック」で展開するとわかりやすいです。
では、「三角ロジック」とは何でしょうか?
〜統合と解釈を行う際に活用できる「三角ロジック」とは何か?」〜
三角ロジックとは、「クレーム(主張)」「データ(根拠)」「ワラント(データの根拠)」の三要素で文章を構成することで、論理的で説得力のある説明ができる方法。形が三角形に似ていることから「三角ロジック」と呼ばれている。
例えば、転倒リスクのある片麻痺患者の歩行について考えてみます。
- クレーム:麻痺側立脚期に膝関節が後方変位し体幹が前傾、さらに体幹の麻痺側への動揺が見られ、転倒リスクがある。
- データ:MMTの結果、麻痺側膝関節伸展は3レベル、麻痺側股関節伸展は3レベルだった。
- ワラント:〇〇(文献著者)らによると、片麻痺患者にとって大腿四頭筋と大殿筋の筋力は歩行の安定性を高める上で重要である、と報告している(仮にこんな文献を検索して見つけられた場合の書き方です)。
上記を、症例レポートの中の「統合と解釈」で文章化すると・・・
本症例の歩行を観察すると、麻痺側立脚期に膝関節が後方変位し体幹が前傾、さらに体幹の麻痺側への動揺が見られ、転倒リスクがあると考えられる。麻痺側立脚期に膝関節が後方変位することについて、MMTの結果、麻痺側膝関節伸展は3レベルだった。また、体幹の麻痺側の動揺について、麻痺側股関節伸展はMMT3レベルだった。〇〇らによると、片麻痺患者にとって大腿四頭筋と大殿筋の筋力は歩行の安定性を高める上で重要である、と報告している。以上のことから、本症例の歩行は転倒リスクがあると考えられる。
必ず、検査・測定で得られた結果と動作観察上の問題点がリンクしていなければいけません。そして、この関係性を言語化していくのが統合と解釈になります。あとは、うまくICFの心身機能・身体構造と活動のところで整理してまとめれば、理学療法評価は終了です。
短期目標や長期目標、さらにプログラム設定は、問題点が整理できていれば、それを目標やプログラムに置き換えれば良いので、簡単なことです。自分の行った評価が正しければ、患者は良くなっていくだろうし、間違っていれば、修正して再評価すれば良いだけです。難しく考えるのではなく、シンプルに考え、文章で書く前に自分の言葉で簡単に言葉にしてみて下さい。それができたら、あとは、専門用語で言語化するだけです。
まとめ
片麻痺患者の理学療法評価も、特別に考える必要はありません。患者の訴えから動作を確認し、それを裏付けるためのデータ収集するだけです。そして、動作と検査結果をつなげる統合と解釈が、理学療法評価の肝になります。
この作業は、やり始めは難しいかもしれませんが、わからなければ指導者に相談すれば良いのです。学生は考えを言語化することに慣れていないです。だからこそ、それを補うためには指導者など、経験者の考えを教えてもらい、マネすることから始めてみるしかありません。頑張って下さい!

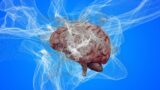


コメント