理学療法士を目指す学生にとっての国家試験は「最終目標」
理学療法士を目指す学生の「最終目標」・・・それは国家試験に合格することです。国家試験に落ちてしまったら、自分の描いた人生設計は崩れ去ります。まずは、この「落ちることができない」状況を認識して下さい。
理学療法士国家試験を控える受験生に問いたい!
- あなたは、受かって理学療法士として働きますか?
- あなたは、落ちてリハビリ助手として働きますか?
やはり、合格率80%前後の国家試験に落ちることは相当ショックなものです。国家試験は6割取れれば合格する試験なので、自分の頑張り次第で結果は付いてきます。受かっても、落ちても、それは自分の責任なのです。
だからこそ、せっかく勉強するなら無駄なことはせず、短時間で効率的に勉強していくことが得策だと思います。臨床実習中だからといって、国家試験勉強を後回しにすることは避けたいところです。
ただ、臨床実習はつらく、大変だと考えている学生は多いのも現実です。理不尽な指導者は、まだまだたくさんいますからね。特に、虐待の連鎖と同様、自分が実習生時代に理不尽な指導者から指導を受けた指導者は、どうしても、同じことを考え、教育してしまうように感じます。
臨床実習がつらくなったPT実習生は、以下の私の体験談「臨床実習が怖くなったPT実習生へ!認知行動療法を学んで心を軽くする方法」を読んでみて下さい。
いずれにしても、国家試験に合格することが学校に入った「最終目標」なので、親や親戚、あるいは自分で貯金をし、高い学費を出して入学したからには、免許だけは何が何でも取って下さい!
国家試験の知識を臨床実習の経験に活かすことを考える!
私は、これまでにプロフィールを確認してもらえば分かりますが、様々な職場で働いてきました。臨床実習指導者や養成校教員としての経験から、理学療法士を目指す学生の最終関門である国家試験の勉強は、臨床実習と絡めて勉強していくことが効率的な勉強だと思っています。特に、最終学年の年は、多くの学生が臨床実習を行い、同時に国家試験の勉強を行うため、本当に時間がありません。
国家試験の勉強を効率的に進めるためには、国家試験の知識を臨床実習の知識に活かすこと、逆に、臨床実習の経験を国家試験の知識につなげることを考えながら勉強した方が効率的であり、記憶に定着して忘れないです。「この知識は、臨床ではどのように活かされるのか?」を常に考えながら勉強することは、記憶の定着の助けとなります。
では、具体的にどうやるのでしょうか?
例えば、患者に大腿四頭筋のMMTを測定する場面を想像して下さい。
この時、脳は大腿四頭筋が収縮するよう命令します。
運動野から内包後脚を通り、中脳の大脳脚、橋の橋縦束、延髄の錐体を通って錐体交叉し、脊髄の側索を通って前角細胞でシナプスを作って伝達、運動神経を経て筋へ刺激を伝える、という一連の知識が国家試験の知識であり、これを患者を通してイメージできるかがポイントになります。
脳から筋収縮までの知識の詳細は、別の記事「錐体路の知識を筋力評価、筋力トレーニングに役立てよう!」で解説しています。
臨床実習中に患者を通して学んだ知識は、国家試験の勉強において必ず役立ちます。先ほど説明した筋収縮のメカニズムも、臨床実習の中で関連させて勉強していれば、それがエピソード記憶として記憶に定着し、実際、国家試験中にアウトプットできると思います。
私が考える国家試験の効率的な勉強法・・・まずは専門基礎3科目を仕上げる
私は、養成校で働いていた時に国家試験対策の責任者をしていました。当たり前ですが、国家試験を勉強するには過去問が必要です。理由は簡単です。国家試験の全体像を把握するためです。国家試験の問題を見たことがない1年生や2年生は、わからなくても良いので、1度ペラペラと見てみて、わかる問題を解答してみて下さい。
特に、全100問の中で、51番から74番の専門基礎3科目(解剖学、生理学、運動学)の問題傾向をよく見ておいて下さい。これが臨床実習で抑えておくべき知識です。そして、この3科目の知識が身に付けば、病気の理解も格段と高まります。つまり、応用できるのです。
理学療法士の国家試験は解剖学、生理学、運動学を仕上げ、その知識を臨床医学へと発展させていきます(この点は作業療法士国家試験も同様です)。つまり、専門基礎3科目を仕上げて、臨床医学の問題に取り組むこと。この基礎さえ習得できていれば、後の専門実地や専門問題である治療などにも応用がきくのです。まずは、この専門基礎3科目をしっかり習得することを目指しましょう。
近年の国家試験の問題は、臨床的な知識が必要だと感じます。国家試験を受験する学生にとっては、それが臨床実習の知識です。私が臨床実習で指導する学生には、常々、国家試験を見据えて臨床実習に取り組んでほしいと伝えています。
そのため、臨床実習には必ず、自分が現在使っている国試本を持参させています。そして、自分が実習で学んだ知識は、国試本のどこに書かれているかを徹底的に意識させます。そうすることで、国家試験当日も、実際に出会った患者や利用者を通して学んだ知識が想起され、問題を解いていけると思います。何かに関連させて覚えた知識は、決して忘れないのです。
解説の詳しい過去問を取り扱った国試本を入手し、今後の戦略を立てる。
では、具体的にどうすれば良いのか?
孫子の兵法の有名な言葉に、以下のような一説があります。
彼を知り己を知れば百戦して殆うからず
(かれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず)
これを、国家試験に当てはめてみましょう。
過去の国家試験の問題傾向を知り、自分の今現在の実力を把握していれば、模擬試験だろうが、国家試験だろうが、何回行っても不合格点をとることはない。
ということです。
だからこそ、国家試験の勉強は、過去問に沿った勉強をしなければならないのです。逆に、過去問を無視すれば、的外れな勉強をしていることとなり、無駄な勉強をしてしまうことになります。時間の限られた学生にとっては、これは致命的です。
つまり、まずは過去問ベースの解説の詳しい国試本を入手して下さい。それが、国家試験の勉強を始める際の、第1に行うべきことです。
どの国試本を選べば良いか? おすすめはQB一択!
では、国家試験の勉強は、何から始めれば良いのでしょうか?
そこで、次にやることは、国試本を入手することです。
国試本には、主に、以下のようなものがあります。
- クエスチョンバンク(QB)
- 国試の達人(国達)
- 必修ポイント
他にもいろいろな書籍が出ていますが、特に、時間のない学生やあまり点数が伸びてこない学生には、クエスチョンバンク(QB)がオススメです。
理由は、国家試験の「どの分野」の「どんな問題」が出題されて、「どのくらいまで掘り下げて勉強しなければいけないのか」の過去問分析が、解説として既になされており、かつ、とても見やすくわかりやすいからです。過去問分析は、受験勉強やどんな資格試験の勉強でも大鉄則ですので、その意味でQBは全てを兼ね備えていると思います。
一部QBに対して「内容が薄い」など、批判的な意見もあります。しかし、国試勉強は、膨大な知識を試験当日まで定着させ、過去問から大きく外れることなく勉強していくことが必要です。その点、QBは過去問の解説が詳しく、図表が多く、とても見やすくて、わかりやすいと思います。もし、内容が薄いと感じるのであれば、自分で内容を濃くしていけば良いのです。
内容を濃くするために、解説が不十分なところは自分で調べてQBに書き込み、自分オリジナルの国試本に育てていく気持ちで勉強していきます。そして、十分育ったQBを共通と専門の2冊を試験会場に持っていけば、直前の見直しはもちろんのこと、自分の努力の結晶としてお守りにもなります。自分オリジナルのQBを育て上げて下さい。これは、誰かにもらったものでは絶対にダメなのです。
国試本の使い方は? 問題を読んで、すぐに答えと解説を読むこと!
記憶の定着には、問題の「理解→暗記→反復」という一連のプロセスが欠かせません。それには、見やすく、図表が多く、解説が詳しいなど、自分1人で理解しながら自習ができる教材を、最後まで繰り返し使っていくことが重要です。この「理解する」ことがポイントです。理解できなければ「暗記」へと進まないので、QB1週目は「理解する」ことに重点を置きます。
QBは、内容が全て過去問であり、図表が多く、設問1つ1つに解説が書かれています。しかし、解説の中には、分からない言葉や内容が不十分なところもあるので、そこは自分で調べたり、分かる人に聞いたりして書き加えていきます。これが、前述したQBを自分オリジナルの国試本に育てていくことです。先輩にもらう人もいますが、それは、あくまで先輩が育てた国試本です。自分で買って育てて下さい。
私の実際のやり方です。
私のQBの使い方は?
- 問題を読み、すぐに答えを確認する。
- 解説を読みながら、正しい設問はそのまま暗記し、間違えた設問は修正して、それを理解しながら暗記する。理解していれば、次の問題に進む。
- 分からない言葉や理解できない説明は、自分で調べたり、分かる人に聞いたりして、どんどん書き加えていき、理解するまで行う。
- 上記1〜3の作業を、1冊終わるまで進めていく。進め方は1ページ目からではなく、興味ある問題、臨床実習に関連した問題から進め、最終的に1冊終わるように進めていく。
注意点は、問題文には書き込まないことです。書き込むのは、あくまで解説文です。問題を解きながら、わからない単語があったらそれを調べて空白に書き込んでいきます。また、図で示した方が良いなら図を書いておきます。この調子で、とりあえず1問1問を地道に取り組み、1冊(1周)を終わらせていきます。1周終わったら2周目に入り、できれば10周以上行ってほしいものです。
もちろん、国試本は相性なので、QBが生理的に無理という人は、その他の本を使っていくのでも構いません。ようは、国試範囲の知識を記憶に定着できれば良いのです。
まとめ
国家試験の勉強は積み上げ型です。おそらく、問題作成者もそんな意図を持っていると思います。だから慌てず、まずは、解剖学、生理学、運動学を仕上げていくことが重要です。ここが仕上がっていると応用がききますし、臨床実習でも使えます。とにかく、専門基礎3科目を仕上げることから、国家試験勉強を進めてみて下さい!
そして、知識の「点」から、つながりの「線」、全体の「面」とする勉強を行って下さい。
私が、このブログで理学療法士を目指す学生に伝えたいことは、「点」を「線」や「面」にしていく勉強です。ほとんどの学生は、国試本を中心に勉強しています。これは、「点」を作る作業です。
学問の面白さは、自分の勉強したことが実生活に活かされる、また、理学療法士であれば患者に活かされるところにあります。例えば、先程、例に挙げた筋収縮のメカニズムを理解できれば、自分や患者の筋トレに活かすことができます。
あくまで、今行っていることは国家試験のための勉強ですが、それが後々、活かされることに学生は気づいていません。日々の勉強や臨床実習でいっぱいいっぱいだからです。もったいないことです。
臨床実習の中で、よく勉強している学生でも、知識量はあるのですが、いざ、つながりの説明を求めると答えられません。しかし実際、「点」を「線」や「面」になるよう誘導してあげると、勉強の面白さに気づき、新たな気持ちで勉強に取り組む学生は少なくありません。
「点」を「線」や「面」にできると、もう忘れませんし、知識は定着したと言っても良いと思います。しかし、ただ闇雲に知識を蓄えていては、すぐ忘れます。国試勉強を、実際は自分の体の中で起こっていることとして、そして、自分の身近な例(臨床現場)に関連させながら人体の仕組み(メカニズム)を理解することとして勉強できれば、解剖学、生理学は面白い学問だと気づくでしょう。そうなれば国試問題も難なく解くことができると思います。
臨床実習の中で、私が、
「筋収縮ってどのように起こるの? 説明してみて!」
と質問したら、どう答えますか?
この問いに、1つ1つ丁寧に答えられるよう、期待しています。
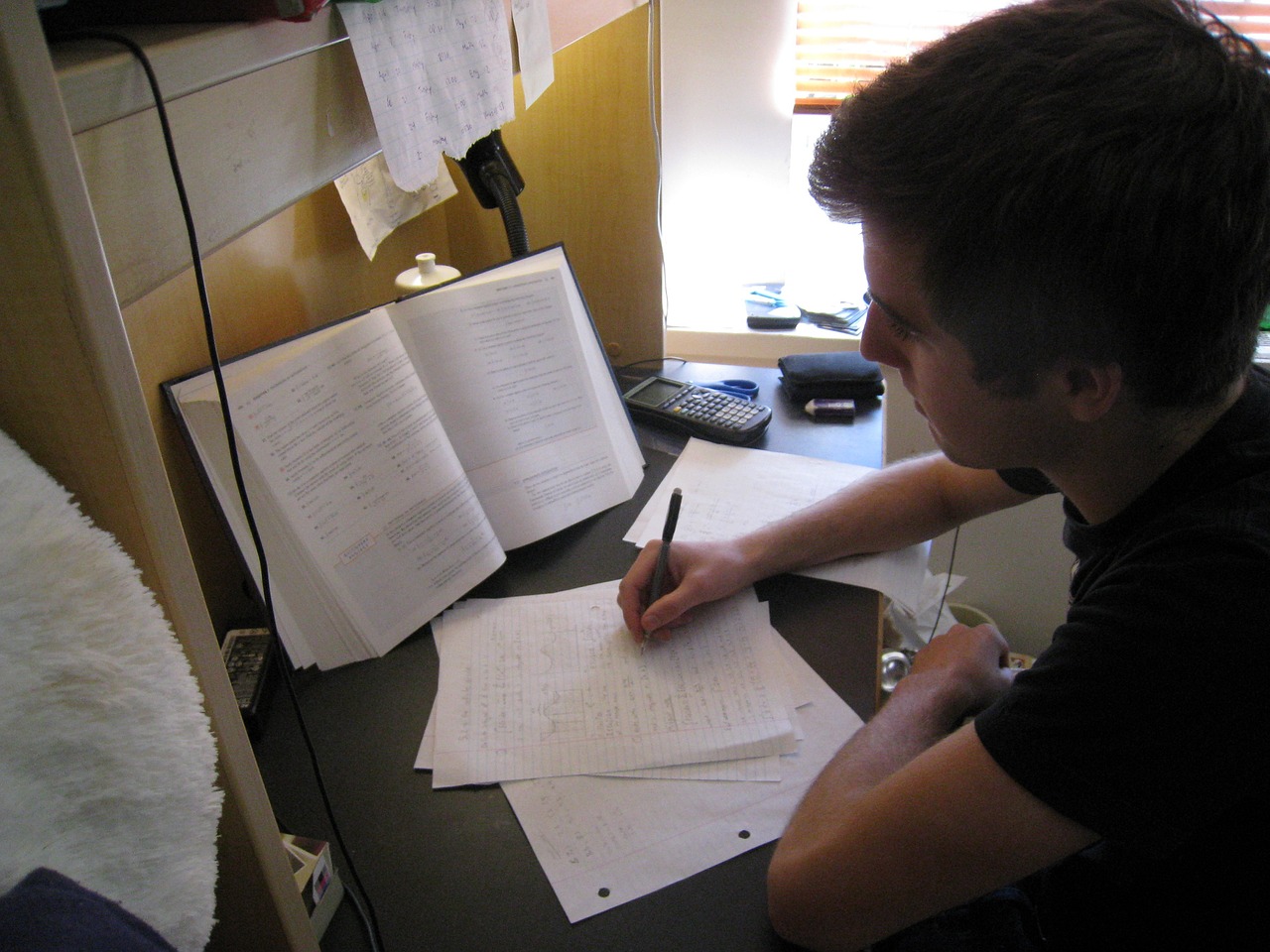

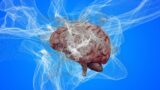


コメント